専門医が解説!過敏性腸症候群(IBS)について

過敏性腸症候群について
検査で異常ないのに続く、腹痛と便通異常
「通勤・通学の電車でお腹が痛くなる」「大事な会議の前に限って下痢をする」「便秘と下痢を繰り返してスッキリしない」…その症状、ただの体質ではなく「過敏性腸症候群(IBS)」という病気かもしれません。
過敏性腸症候群は、決して珍しい病気ではなく、日本人のおよそ10人に1人が悩んでいると言われています。大腸がんなどの異常が見つからないにもかかわらず、ストレスや食事などが引き金となり、つらい症状が長く続きます。当院では、消化器内科専門医が詳細な問診と必要な検査を行い、患者さんのタイプ(便秘型・下痢型など)に合わせたお薬の処方や、食事・生活指導を行い、症状とうまく付き合いながら快適な日常生活を送れるようサポートいたします。
- 専門医による診断
- 大腸カメラ検査
- タイプ別の治療
- 食事・生活指導
🦠 過敏性腸症候群とは?

過敏性腸症候群(IBS)は、内視鏡検査などで腸に異常がないにもかかわらず、腹痛や便通異常が数ヶ月以上続く病気です。20代〜40代の若い世代や女性に多く、ストレスなどで脳と腸の連携が乱れることが原因と考えられています。
🤒 主な症状
最大の特徴は「腹痛」と「便通異常」がセットで起こることです。排便によって痛みが和らぐことが多いのも特徴の一つです。
下腹部の差し込むような痛み、急な便意(切迫感)。排便後に少し楽になることがあります。
泥状〜水様便。特に朝や食後に起こりやすく、突然の激しい便意を伴うことがあります。
コロコロとした硬い便(兎糞状)。排便しても残便感があり、強くいきんでしまうことがあります。
お腹が張って苦しい、ガスが溜まっている感じがする(おならやゲップが増える)。
⚠️ 危険なサイン
以下の症状がある場合は、過敏性腸症候群ではなく、大腸がんや炎症性腸疾患など別の病気の可能性があります。速やかに医療機関を受診してください。
- 🩸 血便が出る
- 📉 体重が急激に減った
- 🤒 発熱がある
🦠 主な原因とメカニズム

過敏性腸症候群のはっきりとした原因はまだわかっていませんが、一つの原因ではなく、いくつかの要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
脳と腸の連携異常
私たちの脳と腸は自律神経を通じて情報を交換しています。ストレスや不安、睡眠不足などがこの連携を乱すと、腸の動きが速くなりすぎて下痢に、遅くなりすぎて便秘になります。また、IBSの方は腸が敏感になっており、わずかな刺激も脳が「痛み」として強く感じ取ってしまいます。
腸内細菌のバランスの乱れ
私たちの腸の中には、たくさんの種類の細菌がバランスを保ちながら生息しています。食事内容や胃腸炎の影響で、この腸内細菌のバランスが崩れることが、過敏性腸症候群の症状に関係している可能性が指摘されています。
食べ物に対する過敏性
特定の食べ物を食べた後に症状が悪化する方が多くいます。小腸で吸収されにくい特定の糖質が、腸内でガスを発生させ、腹痛やお腹の張りを引き起こすことが知られています。
遺伝的な要因
過敏性腸症候群は家族内で発症することもあり、遺伝的になりやすい体質がある可能性も考えられています。
📋 IBS診断・病型チェック
過敏性腸症候群(IBS)の可能性と、該当する場合はタイプ(便秘型・下痢型など)を確認できます。Rome IV基準に基づいた質問に順番にお答えください。
質問 1 / 5
⚠️ ご注意
このチェックツールは診断の参考としてご利用ください。正確な診断には、医師による診察と検査が必要です。
🏥 診療の流れ

どのような症状がいつから続いているか、排便の頻度や性状などを詳しく伺います。
IBSと似た症状を起こす大腸がん、炎症性腸疾患、甲状腺機能異常などがないか、採血、CT、大腸カメラを行い調べます。
診断がついた場合、便秘型・下痢型などのサブタイプや重症度に合わせて、お薬の処方や食事療法を行います。
🔬 検査と診断

IBSは特定の検査数値で診断できる病気ではないため、国際的な診断基準(Rome IV基準)に基づいた症状の確認と、他の病気(大腸がんや炎症性腸疾患など)ではないことを確認する「除外診断」を組み合わせて診断します。
問診・診察
腹痛と便通異常(便の形や回数)の関係を詳しく伺い、お腹の触診でしこりや圧痛がないかを確認します。
血液検査
貧血がないか、炎症反応(CRP)がないかを調べます。また、甲状腺機能異常(TSH)や糖尿病などの代謝性疾患が症状の原因になっていないかも確認します。
便検査
細菌による感染症の有無を調べます。
腹部レントゲン・超音波検査
レントゲン:便秘型IBSの場合、腸に便やガスがどれくらい溜まっているかを確認します。
超音波・CT:肝臓、胆嚢、膵臓など、腸以外の臓器に痛みの原因となる病気がないかを除外するために行います。
💊 過敏性腸症候群の治療

IBSの治療は、症状の消失(完治)を目指すよりも、「患者さんが納得・満足できる程度に症状をコントロールし、日常生活の質(QOL)を改善すること」が現実的な治療目標となります。
治療は、食事・生活習慣の改善から開始し、改善が不十分な場合に症状に合わせた薬物療法へとステップアップしていきます。
👆 タップして詳細をみる
🏥 基本治療(すべてのタイプ共通)
すべてのタイプの方に共通する「土台作り」です。軽症の場合はこれだけで症状が改善することもあります。
🏃 生活習慣の改善
睡眠不足や質の悪い睡眠は、翌日の腹痛や消化器症状を悪化させます。規則正しい睡眠リズムの確保が重要です。
ウォーキングやヨガなど、中等度の運動(1回20〜60分、週3〜5回)を継続することで、IBSの全体的な症状改善が期待できます。
ストレスは脳と腸の連携(脳腸相関)を乱し症状を悪化させる最大の要因の一つです。リラクセーションや休息を意識的に取り入れましょう。
🍽️ 食事療法
1日3食、決まった時間に食べることで腸の運動リズムが整います。
早食いを避け、よく噛むことで空気の飲み込みを防ぎ、ガスやお腹の張りを軽減できます。
高脂肪食:揚げ物や脂っこい食事は腹痛や下痢を悪化させます
過度なアルコール:特に下痢症状を悪化させる可能性があります
炭酸飲料:腸内にガスを増やし、膨満感の原因となります
カフェイン・香辛料:腸を刺激して症状を誘発することがあります
🥗 低FODMAP食
従来の食事療法で「お腹の張り」や「ガス」が改善しない場合、発酵性の糖質を控える食事法が有効な場合があります。
すべての高FODMAP食品を厳格に控え、症状改善を確認します。
高FODMAP食品を1種類ずつ試し、自分の「トリガー」を特定します。
合わない食品だけを避け、長期的に続けられる食事内容に調整します。
👩⚕️ 栄養士による指導がおすすめ:低FODMAP食は複雑で、自己流では栄養バランスが崩れるリスクがあります。
💊 ベースとなるお薬
どのタイプであっても、腸の土台を整えるために基本薬として用いられます。
目的:ビフィズス菌や乳酸菌などを補充し、腸内細菌のバランスを整えます。
特徴:副作用がほとんどなく安全性が高いため、長期的なコンディション維持に適しています。
🚽 便秘型(IBS-C)の治療
腸の動きが鈍くなったり、便が硬くなって出にくくなったりするタイプです。「便を柔らかくすること」と「腸を動かすこと」を主眼に置きます。
🏃 生活習慣
ウォーキングやヨガなどの中程度の運動(週3〜5回、20〜60分程度)は、腸のガス貯留を減らし、便秘症状を改善します。
🍽️ 食事療法
💡 実践の4つのポイント
繊維を摂っても水分が足りないと便が硬くなります。
水溶性食物繊維のサプリメントで、ガスを増やさずに便を柔らかくできます。
まずは「小麦」と「玉ねぎ・ニンニク」を減らし、主食を「米」に変えましょう。
玄米・ごぼう・ブランなどを食べすぎると、「お腹が張って苦しい」となることがあります。
📋 食品リスト
✅ 積極的に摂りたい食品
🌾 穀物:オーツ麦、白米、そば(十割)
🍎 果物:キウイフルーツ、オレンジ、バナナ
🥬 野菜:オクラ、ニンジン、ホウレンソウ、トマト
🥜 その他:サイリウム、木綿豆腐、チアシード
🚫 控えるべき食品
🍞 小麦:パン、パスタ、うどん、玉ねぎ、ニンニク
🫘 豆類:レンズ豆、ひよこ豆
🍑 果物:プルーン、桃、リンゴ、ナシ
🥛 乳製品:牛乳、ヨーグルト
💊 薬物療法
便の水分バランスを整える薬をベースに、新しい作用機序の薬を積極的に活用します。
習慣性が少なく安全性が高いため、第一選択薬として推奨されています。
腸内で水分を保持し、コロコロ便を適度な柔らかさに整えます。
腸の痛みを感じる神経を鎮める効果があり、腹痛を伴うIBS-Cに特に推奨されます。
お腹が冷えて痛む人や、ガスによる「お腹の張り」が強い場合に有効です。
⚠️ 刺激性下剤(センナ、大黄など)について
即効性はありますが、長期間連用すると効きにくくなります。つらい時だけの「頓服」にとどめましょう。
胃や腸の運動を促進するスイッチ(受容体)を刺激することで、大腸の動きを助けて、便が通過する時間を改善します。整腸剤などと併用することで効果が高まります。
💨 下痢型(IBS-D)の治療
腸が過敏に動きすぎて水分吸収が不十分になり、軟便や下痢が頻発するタイプです。「腸の過剰な動きを抑えること」と「便の水分を調整すること」が治療の柱です。
🏃 生活習慣
下痢型は特にストレスの影響を受けやすいタイプです。リラクセーション法や十分な睡眠を心がけましょう。
激しい運動は逆効果になることも。ウォーキングやヨガなど穏やかな運動がおすすめです。
🍽️ 食事療法
💡 実践の4つのポイント
脂肪は腸の動きを活発にし、下痢を悪化させます。揚げ物や脂っこい食事は避けましょう。
腸を刺激して下痢を誘発します。特に空腹時のコーヒーは避けましょう。
牛乳やヨーグルトは下痢を悪化させることがあります。ラクトースフリー製品を選びましょう。
キシリトール、ソルビトールなどは腸内で発酵し、下痢やガスの原因になります。
📋 食品リスト
✅ 積極的に摂りたい食品
🌾 穀物:白米、オーツ麦、そば(十割)
🍌 果物:バナナ、ブルーベリー、キウイ
🥬 野菜:ニンジン、ジャガイモ、ほうれん草
🥩 タンパク質:鶏肉、魚、卵、豆腐(木綿)
🚫 控えるべき食品
🍔 脂肪:揚げ物、脂身の多い肉、クリーム系
☕ 刺激物:コーヒー、アルコール、香辛料
🥛 乳製品:牛乳、ヨーグルト、アイスクリーム
🍬 甘味料:キシリトール、ソルビトール入り食品
💊 薬物療法
腸の過剰な動きを抑える薬と、便の水分を調整する薬を組み合わせます。
腸の動きを抑えて下痢を止めます。外出前など「ここぞ」という時の頓服としても有効です。
水分を吸収してゲル化し、軟便を適度な硬さに整えます。
セロトニン受容体を阻害し、腸の過敏な動きと腹痛を抑えます。
腸の緊張を和らげ、腹痛と下痢を改善します。ストレス性の症状に適しています。
腸の中だけで働く特殊な抗菌薬です。腸内の悪い細菌を減らしてバランスを整え、お腹の張り(ガス腹)や下痢を改善する効果があります。特に「お腹が張って苦しい」という方に効果的です。
腸の中で余分な胆汁酸を吸着して取り除くことで、下痢を止めます。下痢型の患者さんの約25〜50%に胆汁酸の影響があると言われており、一般的な下痢止めで改善しない場合に有効な選択肢です。
花粉症や喘息で使われるお薬ですが、腸の「微小な炎症」や「知覚過敏」を鎮める働きもあります。急にお腹が痛くなる、トイレに駆け込みたくなる(切迫感)といった症状を和らげる効果が期待できます。
🔄 混合型(IBS-M)の治療
便秘と下痢が交互に起こる、または混在するタイプです。「腸内の水分バランスを整えること」が治療の核となります。
🏃 生活習慣
症状の変動が激しい混合型では、自律神経を整えるための休息や睡眠、リラクセーション法が特に有効です。
何がきっかけで便通が変化するかを把握するために、排便日誌をつけることが推奨されます。
🍽️ 食事療法
💡 実践の4つのポイント
サイリウムやオーツ麦は下痢時は水分を吸着、便秘時は水分を保持する「二相性」の働きがあります。
小麦ふすま(ブラン)やゴボウなどは、お腹の張りや痛みを悪化させることがあります。
パンやパスタ(小麦)を控えて、お米中心の食事にするだけでも症状改善が期待できます。
混合型では何がきっかけで便通が変化するかが個人で異なります。日記で自分のパターンを把握しましょう。
⚠️ 混合型が特に注意したい食品:小麦・タマネギ・ニンニク(ガスの原因)、牛乳・ヨーグルト(下痢の原因)、キシリトールなど人工甘味料
💊 薬物療法
症状の波を穏やかにする「ベース薬」と、その時々の症状を抑える「頓服薬」を使い分けます。
下痢時は吸水して便を固め、便秘時は保水して便を柔らかくする「二相性作用」を持ちます。混合型の第一選択薬です。
便秘が強い時期に使用。下痢に転じるリスクを抑えながら便秘を解消できます。
即効性がありますが、連用は便秘を招くため控えめに。症状が治まったら減量します。
桂枝加芍薬湯は腹痛に、大建中湯はお腹の張りに有効。便通が不安定な混合型によく用いられます。
便通の状態(下痢か便秘か)に関わらず、しつこいお腹の張りや腹痛がある場合に使われます。腸内細菌によるガスの発生そのものを抑えるため、ガス腹でお悩みの方に適しています。
❓ 分類不能型(IBS-U)の治療
IBSの診断基準は満たすものの、便秘型・下痢型・混合型のいずれにも当てはまらないタイプです。「主な症状への対症療法」が治療の中心となります。
🎯 治療アプローチ
便通が治療の主なターゲットとならないため、「腹痛」や「腹部膨満感」を取り除くことを最優先します。
「便秘寄り」か「下痢寄り」かを推定し、そのタイプに準じて治療することが推奨されます。
🍽️ 食事・生活の戦略
「腹部膨満感(ガス)」や「腹痛」を軽減するために、ガスを発生させやすい食品を優先的に控えます。
🚫 優先的に控える食品
🍞 小麦製品:パン、パスタ、うどん
🧅 ネギ類:タマネギ、ニンニク、ネギ(白い部分)
🫘 豆類:大豆(全粒)、レンズ豆、ひよこ豆
🍬 その他:牛乳、キシリトール等の人工甘味料
✅ 食べてよい食品
🌾 穀物:米(白米・玄米)、オーツ麦、そば(十割)
🥬 野菜:トマト、キュウリ、ナス、ニンジン、ほうれん草
🍌 果物:バナナ、キウイ、オレンジ、イチゴ
🥩 タンパク質:肉類、魚介類、卵、豆腐(木綿)
💡 実践のアドバイス
主食を小麦からお米に変えるだけで、ガスの原因となるフルクタンを大幅に減らせます。
非常に発酵性が高く、少量でもガスや痛みの原因になりやすい食品です。
食事内容と便の状態・お腹の張りを記録し、自分のトリガーを確認しましょう。
💊 薬物療法
便通改善薬よりも、腸の調律を整える薬や痛みを抑える薬が選ばれます。
腸内の水分バランスを調整し、便を「正常な形状」に近づけます。便の状態が不安定なIBS-Uにおいて、ベースの治療薬として適しています。
腸のけいれんを抑え、急な痛みを和らげます。
腸の緊張を和らげ、腹痛を改善します。
お腹の張り(膨満感)やガスが主体の場合に適しています。腸を温めてガスの排出を促します。
💡 自分らしい毎日を

過敏性腸症候群は命に関わる病気ではありませんが、日常生活に大きな影響を与えます。「体質だから仕方ない」と諦めず、適切な治療で症状をコントロールすることが可能です。
IBSの治療は、時に長く、根気がいるものかもしれません。しかし、ご自身の病気と症状の特性をよく理解し、生活習慣を見直し、医師と協力して適切な治療を続けることで、症状は必ず改善の方向へ向かいます。希望を持って、焦らず治療に取り組んでいきましょう。
❓ よくあるご質問
🧠 原因とメカニズム
はっきりした原因は一つではありませんが、「脳と腸の情報交換がうまくいっていないこと」が主な原因です。脳がストレスを感じると腸がおかしくなり、腸の不調を脳が敏感に感じ取ってしまう悪循環が起きています。
腸が敏感になっている(知覚過敏):普通の人が感じない程度のガスや便の動きを、脳が「痛い!」と強く感じてしまいます。
腸の動きが乱れている:ストレスや食事をきっかけに、腸が激しく動いて下痢になったり、逆に動かなくなって便秘になったりします。
腸内環境の変化:食中毒やお腹の風邪、ストレスなどがきっかけで、腸内細菌のバランスが崩れたり、粘膜が弱くなったりしていることも関係しています。
💊 薬物療法について
国際的な基準では、安全性の高いポリエチレングリコール(PEG / 製品名:モビコールなど)が第一選択薬とされています。
日本では酸化マグネシウムも広く使われていますが、お年寄りや腎臓が弱い方には「高マグネシウム血症」のリスクがあるため、海外ではより副作用の少ないPEGが優先されます。
なお、どちらの薬も便を柔らかくする効果はありますが、お腹の痛みを直接取る効果は弱いです。そのため、痛みが強い場合やこれらで効果が不十分な場合は、リンゼス、アミティーザ、グーフィスなどの処方薬が検討されます。
🍽️ 食事・その他の治療
「FODMAP(フォドマップ)」とは、お腹の中でガスを発生させたり、水を溜め込んだりしやすい「特定の糖質(糖分)」のことです。この食事療法は、その糖質を控えることでお腹の調子を整え、自分に合わない食材(犯人)を見つけるための方法です。
① まずは3週間、疑わしいものを全部やめてみる(引き算):パン(小麦)、牛乳、豆類など、ガスを出しやすい食品を一旦すべてストップします。これでお腹の調子が良くなれば、「この中のどれかに原因があった」とわかります。
② 1つずつ食べて、犯人を突き止める(足し算):調子が良くなったら、「今日はパンだけ食べてみる」「次は牛乳だけ」と、1つずつ試します。どの場合にお腹が痛くなるかをチェックします。
③ 自分だけの「OKリスト」を作る:犯人がわかったら、それだけを避けて、他のものは食べるようにします。
※「一生食べられない」わけではなく、自分に合わないものを見つけるだけです。自己流は栄養不足になりがちなので、必ず指導を受けながら行いましょう。
薬で治りきらない場合、脳の緊張をほぐして腸を安心させてあげる「心のアプローチ」がとても有効です。
不安の悪循環を断ち切る(認知行動療法):「また痛くなるかも…」という不安が、さらに痛みを呼び寄せてしまいます。考え方のクセを見直して、脳が痛みを感じにくくする練習をします。
脳と腸をリラックスさせる(催眠療法など):専門家のガイドで深いリラックス状態を作り、「腸が正常に動いている」というイメージを脳に伝えて、過敏さを鎮めます。
脳を休ませる呼吸法(マインドフルネス):「今」に集中する呼吸法などで、未来への不安(予期不安)を和らげ、脳と腸の緊張を解きます。
📚 参考文献
- 日本消化器病学会(編).機能性消化管疾患診療ガイドライン2020―過敏性腸症候群(IBS).南江堂,2020.
- Lacy BE, Mearin F, Chang L, et al. Bowel Disorders. Gastroenterology 2016; 150:1393-1407.(Rome IV基準)
- Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, et al. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol 2021; 116:17-44.
- Fukudo S, Kinoshita Y, Okumura T, et al. Ramosetron reduces symptoms of irritable bowel syndrome with diarrhea and improves quality of life in women. Gastroenterology 2016; 150:358-366.
- Chiba T, Kudara N, Sato M, et al. Colonic transit, bowel movements, stool form, and abdominal pain in irritable bowel syndrome by treatments with calcium polycarbophil. Hepatogastroenterology 2005; 52:1416-1420.
- Chey WD, Lembo AJ, Lavins BJ, et al. Linaclotide for irritable bowel syndrome with constipation: a 26-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate efficacy and safety. Am J Gastroenterol 2012; 107:1702-1712.
- Halmos EP, Power VA, Shepherd SJ, et al. A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2014; 146:67-75.
- Pimentel M, Lembo A, Chey WD, et al. Rifaximin therapy for patients with irritable bowel syndrome without constipation. N Engl J Med 2011; 364:22-32.
- 日本消化器病学会(編).機能性消化管疾患診療ガイドライン2021―機能性ディスペプシア(FD).南江堂,2021.
- Wald A. Treatment of irritable bowel syndrome in adults. UpToDate. Accessed September 19, 2025.
✍️ この記事を書いた人
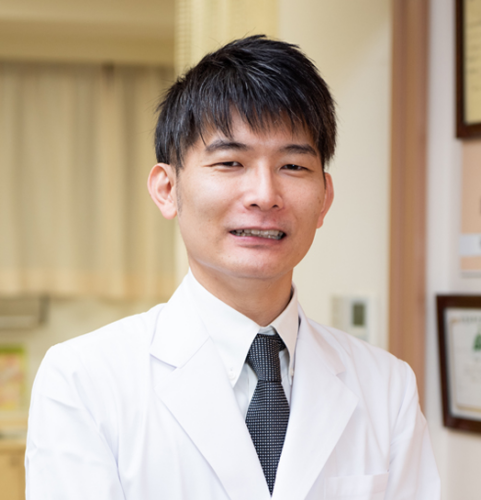
古畑 司(ふるはた つかさ)
保有資格

