専門医が解説!ピロリ菌の検査から治療まで

ピロリ菌について
検査から除菌治療まで専門医が対応
このページでは、胃の不調や将来の病気の不安につながる「ピロリ菌」について解説します。ピロリ菌は胃潰瘍や十二指腸潰瘍、そして胃がんの主な原因となります。
当院では胃カメラによる精密検査から除菌治療まで一貫して対応しております。ご自身の体について正しく理解し、安心して検査や治療に臨むための一助となれば幸いです。
- 胃カメラ検査
- 除菌治療
- 保険適用
- 呼気・便検査
🦠 ピロリ菌って、なに?
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、人の胃の中にすみつく細菌です。多くは衛生環境が整っていなかった時代の幼少期に、家族内などを経由して感染します。

🔄 どうやってうつるの?
ピロリ菌は主に、幼少期に口から入ることで感染すると考えられています。具体的な経路としては、以下のようなものが挙げられます。
👨👩👦 家族内感染
これが最も重要な感染経路と考えられています。ご家族、特にピロリ菌に感染しているお母さんからお子様へ、といった感染(母子感染)が多く報告されています。同じ生活環境で暮らす家族間で、遺伝子的に同じタイプのピロリ菌が見つかることもあり、家庭内での感染が裏付けられています。
💧 糞口感染
ピロリ菌に汚染された水や食べ物を口にすることで感染する経路です。特に衛生環境が十分に整っていない地域では、川の水を飲んだり、十分に洗っていない野菜を食べたりすることが原因となる可能性があります。
💥 どんな影響があるの?
ピロリ菌が胃の粘膜にすみつくと、粘膜を傷つけ、慢性的な炎症を引き起こします。これが様々な病気につながる可能性があります。

🔥 慢性胃炎
ピロリ菌は胃炎の最も一般的な原因です。感染すると、ほとんどの方で活動性の慢性胃炎(常に軽い炎症が続いている状態)になります。これが様々な胃の症状の土台となります。
🩹 胃・十二指腸潰瘍
感染した方の5〜10%が、より深刻な潰瘍を発症します。炎症によって粘膜が弱り、胃酸によって深く傷つけられてしまう状態です。ピロリ菌の除菌治療は、潰瘍の治りを良くし、再発を防ぐ上で極めて重要です。
⚠️ 胃がん
ピロリ菌の感染が長く続くと、胃がんの発生リスクを高めることがある、最も重要な要因として知られています。感染による慢性的な炎症が、胃粘膜の萎縮や腸上皮化生といった「前がん病変」と呼ばれる状態を引き起こすことがあります。ただし、実際に胃がんまで進行するのは感染者の1〜3%未満です。ピロリ菌を除菌することで、胃がんの発生リスクを約半分に減らすことができると報告されています。
🔬 胃MALTリンパ腫
胃にできる稀なリンパ腫の一種で、その90%以上がピロリ菌感染と関連しています。ピロリ菌を除菌することで、このリンパ腫が治癒することがあります。
🩸 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)
血小板が減少する病気の一部で、ピロリ菌の除菌後に血小板数が増加する例が報告されています。
💊 鉄欠乏性貧血
胃の炎症や萎縮によって鉄分の吸収が悪くなり、原因不明の貧血を引き起こすことがあります。
🔬 ピロリ菌の検査方法

💨 尿素呼気試験(UBT)
専用の検査薬を服用し、吐き出した息(呼気)を調べる検査です。ピロリ菌が持つウレアーゼという酵素の働きを検出します。身体への負担が少なく精度も高いため、感染診断および除菌治療後の判定に広く用いられます。
🧪 便中抗原検査
少量の便を採取し、その中に排泄されるピロリ菌の成分(抗原)の有無を調べます。尿素呼気試験と同様に高い精度を持つ検査法です。
🩸 血液・尿検査(抗体測定)
血液や尿を用いて、ピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。抗体は過去の感染歴を示すものであり、現在感染しているかどうかの確定診断や、除菌治療直後の判定には不向きな場合があります。
📷 胃カメラを用いた方法
胃カメラで胃粘膜を観察する際、組織を一部採取して菌の有無を調べます。菌の存在確認に加え、胃粘膜の炎症や萎縮の程度を直接評価できることが最大の利点です。
⚠️ 留意事項
💊 ピロリ除菌について
ピロリ菌が見つかった場合は、将来の胃潰瘍や胃がんのリスクを低減させるために「除菌療法」が推奨されます。

保険での除菌は、胃カメラが必要です。
💊 日本での標準的な治療法
胃酸を抑える薬(P-CAB)1種類と、抗生物質2種類の計3剤を服用します。1次除菌が不成功だった場合は、薬の種類を変えて2次除菌を行います。
💉 1次除菌
P-CAB + アモキシシリン + クラリスロマイシン
1日2回、7日間服用します。
💉 2次除菌(1次除菌が不成功の場合)
P-CAB + アモキシシリン + メトロニダゾール
1日2回、7日間服用します。
🌍 世界的な治療トレンド(参考)
耐性菌の増加に対応するため、海外では以下の4剤療法が推奨される傾向にあります。日本では保険適応外ですが、有効な選択肢の一つです。
🧬 ビスマス四剤療法
P-CAB + ビスマス製剤 + テトラサイクリン + メトロニダゾール
10〜14日間服用します。
⚠️ 副作用と服薬の注意点
除菌治療では、下記のような副作用があることがあります。副作用が出現した場合は、薬を中止し医師や薬剤師へご相談ください。
- 味覚障害、口の中の苦味・金属味(約7%)
- 下痢・軟便(約7%)
- 吐き気(約6%)
- 蕁麻疹・薬疹(約5%)
- 腹痛(約3%)
📋 除菌判定について
除菌薬を内服しても、10〜20%前後のかたで、除菌が失敗することがあります。また、除菌薬は、ピロリ菌の活動を一時的に弱らせるため、菌がいるのに「いない(陰性)」という間違った結果(偽陰性)が出てしまうことがあるため、除菌薬を飲み終えてから最低4週間以上あけて検査を行います。
⭕ 除菌後の判定に推奨される検査
❌ 判定に推奨されない検査
この検査は「過去に感染したことがあるか」を示すもので、除菌後も長期間陽性のままになります。そのため、菌がいなくなったかどうかの判断には使えません。
📅 予約方法
💡 早期発見が未来を作る

ピロリ菌は、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、そして胃がんの主な原因となります。検査でピロリ菌の有無を確認し、陽性の場合は除菌することで、これらの病気にかかるリスクを軽減することが可能です。
ピロリ除菌後であっても、すでに萎縮や腸上皮化生が存在する場合、癌が発生する可能性があるため、定期的な内視鏡検査が推奨されます。
❓ ピロリ菌に関するQ&A
🦠 ピロリ菌の基礎知識
胃の中に生息する細菌の一種です。世界人口の約半数が感染していると言われており、感染の多くは衛生環境が整っていなかった時代の幼少期に起こります。
ピロリ菌は胃の壁に住み着き、胃や十二指腸の粘膜を傷つける酵素や毒素を出して、慢性的な炎症(胃炎)を引き起こします。
実は、ほとんどの人には症状がありません。感染していても、多くの人は一生問題を抱えることなく過ごします。しかし、一部の人では以下のような病気を引き起こすことがあります。
- 慢性胃炎:ほとんどの感染者に見られます。
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍:感染者の5〜10%が発症します。
- 胃がん:ピロリ菌は胃がんの最大の危険因子です(発症は感染者の3%未満)。
- その他:まれに、血小板が減少する病気(ITP)や鉄欠乏性貧血の原因になることもあります。
主に幼少期に、口から菌が入ることで感染します。
- 家族内感染:最も多い経路です。特に母子感染(親から子へ)が多く報告されています。
- 水や食べ物:衛生環境が不十分な場所での井戸水や、十分に洗っていない野菜などが原因となることがあります。
※大人になってから新しく感染することはまれです。
🔬 検査について
主に以下の方法があります。精度を高めるため、複数の検査を組み合わせることもあります。
- 尿素呼気試験:専用の薬を飲み、吐いた息を調べる検査です(精度が高く負担が少ない)。
- 便中抗原検査:便の中にピロリ菌の一部が含まれているか調べます。
- 内視鏡(胃カメラ)時の検査:胃の粘膜組織を一部採取して調べます。
はい、受けられます。ただし、保険適用でピロリ菌の検査・除菌を行うためには、原則として「胃カメラ(内視鏡検査)」を行い、胃炎などの診断を受けることが必須とされています。
※ご家族の病歴などで心配な方で、胃カメラを行わずに検査のみ希望される場合は、自費診療となります。
💊 治療について
「胃酸を抑える薬(P-CAB)」と「2種類の抗生物質」の計3剤を、1日2回、7日間服用します。
- 1次除菌:最初の治療です。
- 2次除菌:1次除菌がうまくいかなかった場合、抗生物質の種類を変えて(クラリスロマイシン→メトロニダゾール)再度7日間服用します。
🍺 お酒についての注意
2次除菌で使用するお薬(メトロニダゾール)は、アルコールと相性が悪く、併用すると「悪酔い」のような強い副作用が出ることがあります。服用中および終了後数日間は禁酒が必要です。
はい、数%〜10%程度の方に副作用が出ることがあります。
- 味覚異常(約7%):口の中が苦く感じたり、金属の味がしたりします。
- 下痢・軟便(約7%):お腹が緩くなることがあります。
- その他:吐き気、発疹など。
副作用が強く出る場合は、服用を中止して医師にご相談ください。
一般的に、1回目の治療で約80〜90%の方が成功します。最近では、胃酸を強力に抑えるお薬(P-CAB)を使用することで、以前よりも成功率が高くなっています。
もし失敗したら?
1回目で除菌できなかった場合(約10〜20%の方)でも、お薬の種類を変えて2回目の治療(2次除菌)を行えば、さらに高い確率で成功します。
💡 成功させるためのコツ
成功率を下げる最大の原因は「薬の飲み忘れ」です。菌を完全に退治するため、症状がなくても自己判断で中断せず、最後まで飲み切ることが最も重要です。
📊 除菌後のフォローアップ
必ず確認検査を受けてください。
薬を飲み終えても、除菌が失敗することがあります(上記の通り10〜20%程度)。また、薬の影響で一時的に菌が隠れてしまうことがあるため、飲み終えてから最低4週間以上あけて、尿素呼気試験などで正確な判定を行います。
リスクは大幅に下がりますが、ゼロにはなりません。
除菌によって胃がんリスクを約半分に減らせると報告されています。しかし、除菌前にすでに胃粘膜の「萎縮」や「腸上皮化生(粘膜が腸のように変化すること)」が進んでいる場合は、除菌後も発がんのリスクが残ります。
そのため、除菌成功後も定期的な胃カメラ検査を受けることが推奨されます。
必ずしも再発ではありません。
血液検査(抗体検査)は、菌そのものではなく「免疫の記憶」を見ています。除菌に成功しても、この記憶(抗体)は何年も消えずに残ることが一般的です。
本当に再発していないか確認したい場合は、抗体の影響を受けない「尿素呼気試験」や便中抗原検査を受けることをお勧めします。
⚠️ 放置するリスク
ピロリ菌を除菌せずに放置した場合、自然に治癒することはほとんどなく、胃の中に住み着き続けて慢性的な炎症を引き起こします。
胃が老化し、がんができやすい状態になる
炎症が長く続くと、胃の粘膜が薄くなったり(萎縮)、性質が変わったり(腸上皮化生)して、「胃がんが発生しやすい環境(前がん病変)」が出来上がってしまいます。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍を繰り返す
薬で一時的に治っても、原因菌がいる限り再発するリスクが高いです。
将来のリスクと感染源
ご自身が将来胃がんになるリスクを持ち続けるだけでなく、ご家族やお子様への感染源となってしまう可能性があります。
参考文献
- Chey WD, Howden CW, Moss SF, et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol 2024; 119:1730.
- Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. Gut 2022.
- Kato M, Ota H, Okuda M, et al. Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection in Japan: 2016 Revised Edition. Helicobacter 2019; 24:e12597.
- Liou JM, Malfertheiner P, Lee YC, et al. Screening and eradication of Helicobacter pylori for gastric cancer prevention: the Taipei global consensus. Gut 2020; 69:2093.
- Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, et al. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterology 2017; 153:420.
- Choi IJ, Kim CG, Lee JY, et al. Family History of Gastric Cancer and Helicobacter pylori Treatment. N Engl J Med 2020; 382:427.
✍️ この記事を書いた人
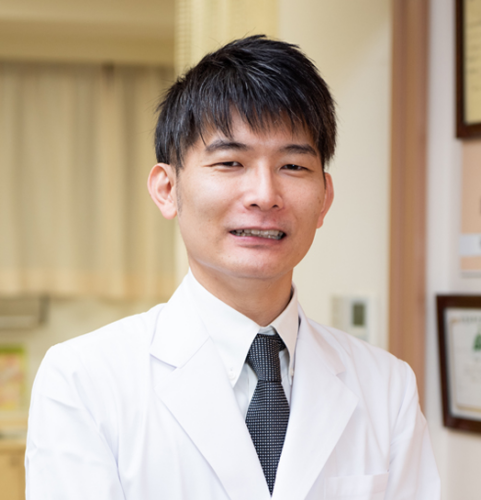
(ふるはた つかさ)
どんな人が検査を受けるべき?
- 内視鏡検査やバリウム検査で胃潰瘍または十二指腸潰瘍と診断された方
- 胃MALTリンパ腫の患者さん
- 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)という血液の病気の患者さん
- 早期胃がんの内視鏡治療を受けた後の方
- 内視鏡検査で胃炎と診断された方
ピロリ菌の検査は、日本の健康保険では、上記のような病気と診断され、原則、胃カメラを受けたうえで、ピロリ菌感染が疑われる場合に検査が認められています。 上記に当てはまらない場合でも、ご家族の病歴などでご心配な方は自費で検査が可能です。

