専門医が解説!便秘について

便秘について
内科・消化器専門医による診断・適切な治療・大腸がんの早期発見
「毎日出なくてお腹が張って苦しい」「便が硬くて出すのがつらい」…便秘は、多くの方が経験する非常に一般的な症状ですが、放置すると生活の質(QOL)を大きく下げてしまいます。
単に「便が出ない」という悩みだけでなく、その裏に大腸がんなどの重大な病気が隠れていることもあります。当院では、内科・消化器専門医が適切な検査を行い、食生活のアドバイスから最新のお薬による治療、必要に応じた大腸カメラまで、お一人おひとりの症状に合わせた最適なケアをご提案いたします。
- 専門医
- 薬物療法
- 大腸カメラ
- 生活指導
🔍 便秘の原因
便秘の原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っていることがほとんどです。
1️⃣ 原発性便秘
はっきりした原因となる病気や薬がない便秘で、主に以下の3タイプに分けられます。
-
腸の動きがスローなタイプ(遅延通過型便秘)
腸の動きが遅く、便が硬くなるタイプ。腸の神経の働きが関係していると考えられています。
-
出口でうまく出せないタイプ(排便障害)
便が直腸まで来ても、出す時に肛門の筋肉が逆に締まってしまうタイプ。いきんでもスッキリせず、指で出す必要があることも。
-
正常通過型便秘
腸の動きに問題はないのに便秘症状があるタイプで、最も多いです。ストレスによる脳と腸の連携の乱れが関係している可能性があります。
2️⃣ 二次性便秘
何らかの病気や、服用している薬の副作用として便秘が起こるタイプです。
-
病気によるもの
大腸の病気:大腸がんや炎症などで腸が狭くなっている場合。
内分泌・代謝の病気:糖尿病、甲状腺機能低下症など。
神経の病気:パーキンソン病、脊髄損傷など。 -
薬の副作用
医療用麻薬(オピオイド)、一部の吐き気止め、鉄剤、抗うつ薬、降圧薬(カルシウム拮抗薬)など、日常的に使われる薬が原因となることもあります。
-
その他
妊娠もホルモンバランスの変化などから便秘の原因となります。
⚠️ 便秘の「危険なサイン」
ほとんどの便秘は生活習慣の改善などで良くなりますが、以下の症状がある場合は、重大な病気が隠れている可能性があります。早急に医療機関を受診してください。
- 血便 ›
- 便潜血陽性 ›
- 原因不明の体重減少 ›
- 貧血症状(めまい・息切れ) ›
- 急に始まったひどい便秘
- 激しい腹痛・嘔吐・発熱
🏥 診療の流れ
症状の問診と触診を行い、お腹の状態を把握します。
レントゲン、CT、血液検査で原因を絞り込みます。
診断を確定させ、大腸カメラなどの精密検査や今後の治療計画を立てます。
最適なお薬の処方と、食事や姿勢などの改善指導を行います。
🔬 検査と診断
正確な原因を知るために、以下の検査を組み合わせて行います。
-
血液検査
貧血›、甲状腺機能、糖尿病、カリウム不足など、便秘の原因となる全身の病気が隠れていないかを確認します。
-
レントゲン検査
腸内にどれくらい便が溜まっているかを確認したり、治療の効果を判定したりするために撮影します。※レントゲン検査のみで便秘のすべての診断がつくわけではありません。
-
CTスキャン
ひどい便秘で腸閉塞(腸の詰まり)が疑われる場合に行います。周囲の臓器や腫瘍が大腸を外側から圧迫(圧排)していないかを確認したり、安全に食事や水分が摂れる状態か、大腸カメラを安全に行えるかなどを多角的に評価します。
-
大腸カメラ(精密検査) ›
便秘において最も怖い病気は「大腸がん」です。これを確実に見逃さないために、直接腸の中を観察することが非常に重要です。特に「危険なサイン」がある方や、40歳以上で一度も検査を受けたことがない方には、強く受診をお勧めしています。
💊 治療
大腸がんなど2次性の便秘を除外したうえで、下記のような対応を行います。
1️⃣ ステップ1:基本対策(すべての方へ)
お薬を飲む場合でも、以下の対策は治療の土台として非常に重要です。
-
食物繊維
1日に20~35gを目標に、野菜、果物、きのこ、海藻などを積極的に摂りましょう。急に増やすとお腹が張ることがあるので、少しずつ増やしてください。特にキウイフルーツやプルーンは有効性が報告されています。
🥝 果物:特にプルーンやキウイフルーツがおすすめです。リンゴ、梨なども効果的です。
🥦 野菜:ブロッコリー、ニンジン、豆類など。
🍞 全粒穀物:玄米、オートミール、全粒粉パンなど。
*腸の動きが極端に遅いタイプの便秘(遅延通過型便秘)の方が食物繊維を摂りすぎると、かえって症状が悪化することがあります。
-
水分
1日に1.5リットル以上を目安に、こまめに水分を摂りましょう。
*心臓や腎臓の病気で医師から水分を控えるように言われている方は、必ずその指示に従ってください。
-
運動
ウォーキングなどの有酸素運動を習慣にしましょう。
-
排便習慣
便意がなくても、毎日決まった時間(特に朝食後が効果的)にトイレに座る習慣をつけます。
-
排便姿勢
トイレで少し前かがみになり、かかとの下に足台を置くなどして「しゃがむ姿勢」に近づけると、直腸がまっすぐになり排便しやすくなります。
2️⃣ ステップ2:お薬による治療
基本対策で改善しない場合、お薬を使います。
-
1. 浸透圧性下剤
便の水分を増やして柔らかくし、排便を促します。まず最初に検討される安全性の高い薬です。
酸化マグネシウム(マグミット、マグラックス)
ラクツロース(モニラック)
ポリエチレングリコール(モビコール)
-
2. 刺激性下剤
浸透圧性下剤で効果が不十分な場合に、追加で使います。腸を直接刺激して動きを活発にするお薬です。長期間使っても安全とされています。
センノシド(プルゼニド)
ピコスルファートナトリウム(ラキソベロン)
-
3. 新しいタイプの便秘薬
従来の薬で効果が不十分な頑固な便秘に対して、腸内への水分分泌を促す新しいお薬を処方します。
ルビプロストン(アミティーザ)
リナクロチド(リンゼス)
エロビキシバット(グーフィス)
⚠️ 注意が必要な状態
-
便塞栓
硬い便が栓のように詰まってしまった状態です。まず病院で詰まった便を取り除き、その後、再発予防のために毎日お薬を飲んで便を柔らかく保つことが重要です。
-
ご高齢の方
心臓や腎臓の持病がある場合、使用する下剤の種類に注意が必要です。特に、市販のリン酸ナトリウム浣腸は重い副作用のリスクがあるため、自己判断での使用は避けてください。
💡 便秘のお悩み、一人で抱えないでください

「たかが便秘」と思われがちですが、つらい症状が続くと生活の質は大きく下がりますし、その裏に大腸がんなどの重大な病気が隠れていることもあります。
当院では、経験豊富な消化器専門医が丁寧に診察し、お一人おひとりの原因に合わせた最適な治療をご提案いたします。必要に応じて大腸カメラ検査も行い、病気の早期発見に努めています。
池尻大橋駅徒歩3分、渋谷から一駅。三軒茶屋・中目黒からも好アクセスです。少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。スタッフ一同、皆様のご来院を心よりお待ちしております。
参考文献
- 日本消化器病学会:慢性便秘症診療ガイドライン 2017.
- Müller-Lissner SA, et al. Myths and misconceptions about chronic constipation. Am J Gastroenterol 2005; 100:232.
- Suares NC, Ford AC. Prevalence of, and risk factors for, chronic idiopathic constipation in the community: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2011; 106:1582.
- Kamm MA, et al. Oral bisacodyl is effective and well-tolerated in patients with chronic constipation. Clin Gastroenterol Hepatol 2011; 9:577.
- Rao SS, et al. Obstructive defecation: a failure of rectoanal coordination. Am J Gastroenterol 1998; 93:1042.
- Tabbers MM, et al. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 58:258.
✍️ この記事を書いた人
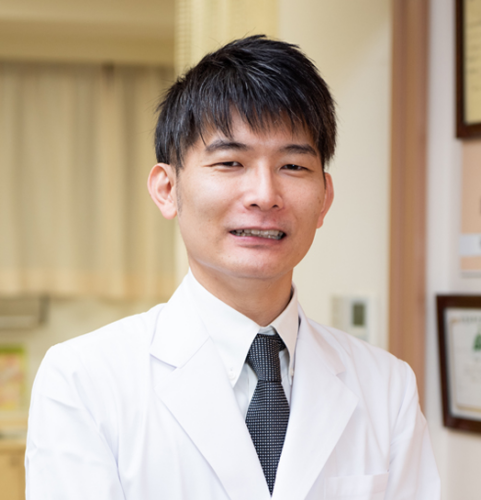
(ふるはた つかさ)

